映画『ノマドランド』に見るポストヒューマン像

映画『ノマドランド』は2008年に起こった経済危機の影響で、持ち家を失い車上生活を余儀なくされた人々を描いています。ノンフィクションである『ノマド: 漂流する高齢労働者たち』がベースになっており、リアリティのある描写が印象的ですが、貧困や格差社会を糾弾するような内容には感じませんでした。
リーマン・ブラザーズによる無謀な住宅ローン販売に端を発する世界的不況のあおりを受けて生活が一変してしまった。そんな主人公の物語というと、やり場のない怒りや悲しみ、不正を許さない正義がテーマになりそうです。でも、そんなことは描かれません。それは何故でしょう?
この映画で感じるのは「何か新しいことの始まり」の予感です。それは何なのでしょう?
(以下、ネタバレあり)
Amazonの描かれ方
車上生活を始めたファーンはAmazonの物流倉庫で臨時雇いとして働き始めます。実際にAmazonはCamper Forceというプログラムを持っていて、オートキャンプ場に宿泊する人々を集め繁忙期の季節労働者として採用しているそうです。ここでファーンは同じ車上生活を送る人たちと知り合い、彼らのコミュニティに接する機会を得ます。
Amazonといえばファーンがいまの生活を始める原因を作ったリーマン・ブラザーズと同様、グローバル資本主義の代表選手です。しかし、この映画でAmazonは労働者を搾取する強欲な企業として描かれているわけではありません。もちろん優れた労働環境を提供する人間味あふれる企業として描かれている訳でもありません。それは、ただ「環境」として描かれています。車上生活者が季節ごとに集い、生活の糧を得、限られた交流を行う「環境」です。そこではAmazon(的な資本主義を含めて)を否定も肯定もしていません。
ファーンは旅の途中でアメリア中西部の砂漠や海岸や森などを訪れ、その美しい景色が描かれますが、Amazonもこれらの景色と同じようにファーンの背景として描かれます。美しい砂漠や海も、時には灼熱や荒波で人々を寄せ付けない姿を現します。グローバル資本主義もその行き過ぎによって災禍を引き起こしますが、それは、砂漠や海や森と等価なのかもしれません。
自然との関わり
ファーンは職を求めて旅しますが、アメリカ各地の美しい自然を一緒に体験できるのも、この映画の醍醐味になっています。砂漠の美しい夕焼け、巨大な岩山の国立公園、巨木が茂る森林、激しい波が打ち寄せる海岸、どれも印象的なものばかりです。
この美しい景色に感情移入していくことになりますが、そこには、何かいつもとは異なる感覚が付きまといます。そう、ファーンと一緒に周っている私達は「ツーリスト」ではないということです。彼女にとっては生活のため、生きるための旅なのです。でも、それは悲壮感を伴うものではありません。動物達が生きるために移動するのに感傷的になったりしないようにファーンの旅も淡々と続きます。
それは、生きることと自然が同じレイヤで語られているということです。現代人は自然を何か有難い特別なもののように感じるか、あるいは、それと対峙してコントロールしてやろうと考えるかのどちらかです。そもそも人間の営みも自然の一部であったのですから、本来はファーンの視点こそが「自然」なはずです。そんな「自然」な視点で見た自然に私達は改めて感動するのです。
友人・家族・恋人
ファーンは旅の途中で出会う人々に共感し時には行動を共にします。人々もまたファーンを思いやりを持って迎え入れます。彼女は車上生活を始めてから3回「家で暮らさないか」と誘われます。友人と家族、そして恋人からです。旅の途中で出会うこれらの人々とのコミュニケーションは彼女を元気付けます。彼女が生きていくうえでの具体的な力となっていたかもしれません。でも、彼女はその誘いをすべて断ることになります。そうした人々と継続した関係を作ろうとはしません。以前のあり方には戻れなかったのです。車上生活を始めた彼女に訪れた変化を一番象徴していることです。
夫に先立たれ、止む無く車上生活を始めた彼女は、夫との思い出が残る家財道具を倉庫に預け旅に出ます。それは夫との生活にアイデンティティを見出していたということです。夫を失ったいま、新たなアイデンティティは友人や姉、新しい恋人との生活の中には無かったのです。ノマドとなった彼女が見出したアイデンティティとはどのようなものだったのでしょう?
「最後のサヨナラはあり得ない」ということ
車上生活者の友人が亡くなり、コミュニティの仲間と見送ったあと、コミュニティの年長者は言います。
「我々はサヨナラは言わない」
「実際、サヨナラを言っても半年後や5年後にばったり会うことになるんです」
「なので、また、どこかで会いましょう“See you down the road”と言います」
ノマドは自分が定住する土地を持ちません。所属する組織や家族も持ちません。そんな彼らは半年ぶりに会う友人や5年ぶりに会う友人との関係のなかに生きています。旅する道や自然環境との関係のなかで生きています。そして、Amazonなど人工物との関係のなかで生きています。
その関係は時に強まり、時に途切れ、また繋がりを繰り返します。そのような揺れ動く関係そのものがアイデンティティであったなら誰かと永遠にサヨナラということは無いのです。
そして、それは死者に対しても同じなのです。
そして、ポストヒューマンへ
哲学者のロージ・ブライドッティは既に「人間」という枠組みの有効性は失われ、我々は「ポストヒューマン」になっているといいます。それは高度に情報化しグローバル化した社会と「人新生」と言われる地球環境の大きな変化を受け、従来「人間」と考えられていた概念が修正を迫られているというものです。
近代以降、主体は個人に帰属してきました。また、個人は法人や国や民族などに所属することでそれをアイデンティティとしてきました。これが、男性、白人、ヨーロッパ中心の世界を作り上げてきたのです。そこから、健常者と障がい者、富める者と貧しい者、男性と女性の区分が生まれます。このような個人主義の障害を排除するために、彼女はノマド的な主体のあり方を提起します。それは、個人や所属する集団に固定されたものではなく、ながれうつろう他のものとの関係のなかに作られるものです。自分と周りの生物や非生物との関係のなかに新しい主体を見出します。
「ノマドへの生成変化のプロセスが含意するのは、自らを世界の中心だと捉え、伝道師を買って出るヨーロッパの役割を拒絶することである。」
自らを世界の中心だと捉えたヨーロッパ文明の最果てがリーマン・ブラザーズでありAmazonだとすると、この映画で描かれるノマド的主体はこれを拒絶するというよりも、それさえも包含するような視点を私達に示してくれます。
久しぶりにネバダ州の家に戻ったファーンは家財を処分して再び旅にでます。これがポストヒューマンになった瞬間ではなく、彼女は既にポストヒューマンだったのかもしれません。そして、それは私達すべてに言えることなのかもしれません。
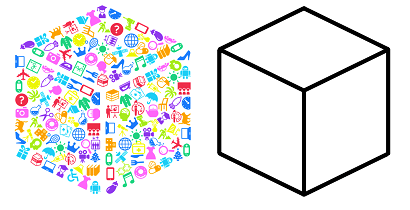
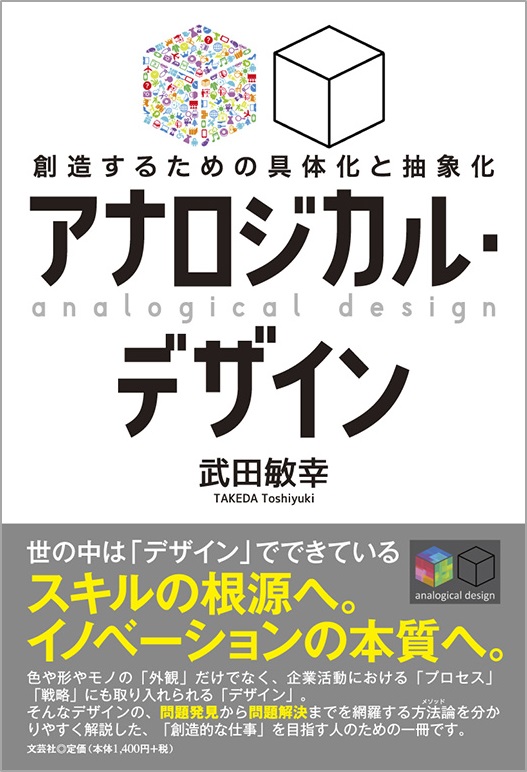



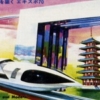




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません