モダニズムから考える『真夜中のドア〜stay with me』のリバイバル
1979年に発売された松原みき『真夜中のドア〜stay with me』がSpotifyのバイラルチャートで急上昇し、2020年12月には世界1位となりました。アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、スウェーデン、オーストラリア、インド、シンガポール、フィリピンなど各国のバイラルチャートでも1位を獲得したということです。
素敵な楽曲は時代も国も超えて聴かれるという当然のことなのですが、数少ない私のCDコレクションの一枚だったので、感慨深くこのニュースを聞きました。
「どこにも無い都市」への憧れ
『真夜中のドア〜stay with me』は失恋の歌ですが、どこかドライであまり悲壮感がありません。"stay with me"という英語のフレーズが心地よくリフレインし、歌詞にも自立した女性の客観的な視点が感じられます。70年代に全盛だった演歌や歌謡曲とは明らかに違う雰囲気です。
この曲を聞いて感じるのは、当時も今も、洗練されていて、上品で、最新の流行を感じさせる、要するに「都会的」ということです。シティ・ポップというジャンルに入るようですが、シティ・ポップは「都市と自分たちとの関係性を描く」ジャンルと言われています。シティ・ポップでは「ショーウィンドウ」や「高速」や「飛行場」など都市のアイコンが歌われ、都会の風景が切り取られます。そして、その都市はニューヨークでもロサンゼルスでも東京でもなく、どこにも無い架空の都市なのだと思います。架空の都市とすることで、実際には過酷な都市生活の現実から離れ、自由にイメージの都会に「憧れ」ることができるのです。
モダニズム
そんな、都会への憧れとは何なのでしょう?
しかも、「どこにも無い都市」に惹かれるというのはどういう意味があるのでしょう?
私達は、都市は「カッコいい」もので、田舎は「ダサい」ものというような価値観(最近はそんな風潮も無くなってきましたが...)を何か当然のように受け入れています。18世紀に産業革命が始まる前まで、イギリスではほとんどの人が農村に住んでいました。そのころはまだ都市が「カッコいい」などという考え方はなかったと思います。19世紀中葉まで続いた産業革命の後では人口分布が逆転し70%以上が都市に住むようになりました。国は労働者を集めるため都市生活の素晴らしさ喧伝したでしょうし、実際に都市に住み始めた人々は「住めば都」というように新しい環境を肯定するしかなかったのだと思います。
そうして徐々に作られた都市生活の価値観は19世紀末から20世紀中葉にかけてのモダニズムによってある意味完成されます。モダニズムは、文学や音楽、絵画、建築など様々なジャンルに跨る芸術運動ですが、どのジャンルにも共通しているのは、それまでのヨーロッパの古い伝統である君主制や封建主義などの権威主義的な思想や体制を拒絶し、現代に相応しい価値観を提起したということです。
例えば、建築の分野では、それまでの歴史的な意匠を否定し、機能主義、合理主義が追求されました。コルビジェやミース、グロピウスなどの無駄を省き利用者視点で機能的に造られた建築は、個人を主体にする近代に相応しい価値観として世界中に広まりました。
何故、都会に憧れるのか?という疑問には、この当たりにヒントがありそうです。つまり、産業革命以降、個人主義や合理主義が普及し、これを体現している造形物やライフスタイルを美しいとする価値観がモダニズムを契機に支配的になったということです。そして大事なのは、モダニズムは「古い伝統を拒絶する」ということです。つまり地域社会に残る共同体的なものや権威主義的なものは排除されることになりました(田舎は「ダサい」)。
そしてモダニズムにおける、現代以降の「何か新しい」ものを肯定し「古い伝統」を排除する態度は、結果的に興味深い副作用を生み出します。
過去を否定し、現在以降を肯定するということ

Wikipediaより ウェストミンスター宮殿 Mайкл Гиммельфарб (Mike Gimelfarb) – 投稿者自身による作品
イタリアで17世紀まで続いたルネサンス建築は古代ローマの建築様式を取り入れたものでした。18世紀イギリスのネオ・ゴシック様式は12世紀フランスのゴシック建築を復興する運動でした。ヨーロッパには過去を再解釈することで、新しい表現を創造してきたという伝統があります。
これは、建築だけではなく、人間の営みは多くの場合、過去を参照しています。しかし、「古い伝統」を排除するモダニズムには、現代から先、つまり未来しかありません。古代ローマ時代も12世紀のゴシック建築も理想とすることができないのです。未だ到来していない未来に価値を置くというのは、「無いもの」を理想とするということです。
シティ・ポップでは、どこにも無い「イメージ」の都市への憧れが作用していました。これはモダニズムが標榜した「現在以降」の「何か新しいもの」を肯定することと相似形です。
もう一つの疑問「どこにも無いものに惹かれるのはどのような意味があるのか?」ということについてもモダニズムのなかに答えがありそうです。モダニズムもシティ・ポップも、今まで存在したことないイメージを理想としています。そして、その理想は決して実現することがないので無限に人々を駆動することができるのです。イメージへの「憧れ」なので、それは決して実現しません。しかし、イメージであるからこそずっと「憧れ」させることができます。
モダニズムの時代、19世紀末から20世紀中葉というのは資本主義が世界を覆った時代でもあります。資本主義がゴールの無い資本獲得のゲームということと、モダニズムの実現しない理想とが相似形なのも偶然ではないのかもしれません。シティ・ポップはまさにそんな時代の価値観を体現しているのではないでしょうか。
インドネシアに流れるジャパニーズ・シティ・ポップ
『真夜中のドア〜stay with me』の世界的なリバイバルはインドネシアが発端です。Rainych(レイニッチ)というアーチストがカバーしたことから火がつきました。では、このリバイバルにも、モダニズムの価値観が影響していたのでしょうか?
都会への憧れ、それも、どこにも無い都市への憧れを、1970年代の日本と同じように抱いていたかというと、それは、まったく違うのだと思います。インドネシアでは、既に十分都市化が進みグレーター・ジャカルタの人口は約2,400万人で世界第2位の規模になっています。住人達は、世界の他の国と同じように、理想とした都市生活と現実とのギャップを日々見つめているのでしょう。
そんな、都市の日常生活で日本のシティ・ポップはどのように聴かれたのでしょうか。
「昔、そんな都会の生活に憧れたことがあった」
「でも、それはどこにも無い都市だったんだ」
という感慨ではないかと空想します。
過去に理想としたものが本当は存在しなかった。でも、それを懐かしく思い出す。それは、言葉の本当の意味での「ノスタルジー」なのかもしれません。インドネシアの人達はそんなノスタルジーをポジティブに感じることができる。それが、世界中の人々の共感を呼んだのかもしれません。
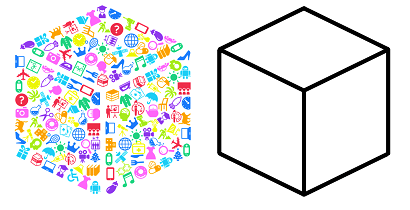



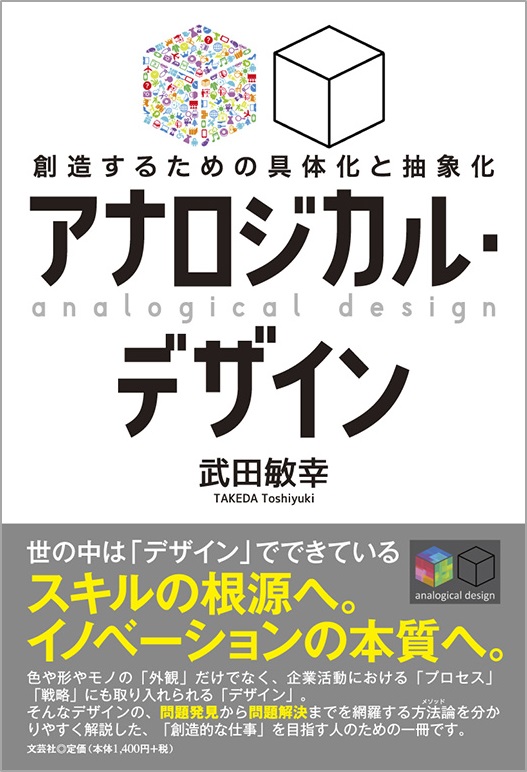



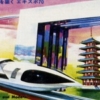





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません