メソッド
アナロジカル・デザインのメソッドページです。以下のメニューからメソッドの詳細を参照できます。
| メソッドの概要 |
|
| (フェーズ1)ターゲットの具体化 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フェーズ2)ターゲットの抽象化 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フェーズ3)マッチングと問題定義 |
|
|||||||||||||||||||||
| (フェーズ4)ベースから適用する内容の具体化 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フェーズ5)解決策の総合とプロトタイピング |
|
||||||||||||||||||||||||
analogical design - アナロジー思考による創造するためのデザイン
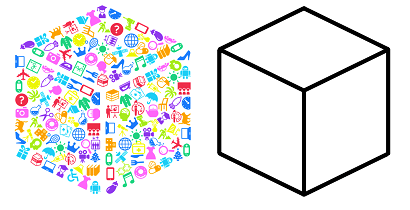
アナロジカル・デザインのメソッドページです。以下のメニューからメソッドの詳細を参照できます。
| メソッドの概要 |
|
| (フェーズ1)ターゲットの具体化 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フェーズ2)ターゲットの抽象化 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フェーズ3)マッチングと問題定義 |
|
|||||||||||||||||||||
| (フェーズ4)ベースから適用する内容の具体化 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フェーズ5)解決策の総合とプロトタイピング |
|
||||||||||||||||||||||||