ラジオ-引き算のデザイン
以前から漠然と「ラジオは無くならないのでは」と思っています。テレビが衰退し、インターネットが更に進化しても、ラジオは聴かれ続けるように感じます。皆さんはどう思いますか?
Contents
ラジオ文化の定着
初めてのラジオ放送は1906年の12月24日、クリスマスイブのことだったそうです。米国マサチューセッツ州の無線局からレジナルド・フェッセンデンが自分で演奏したクリスマスソングを放送しました。
それからあっという間に世界中に広がったラジオは、事件を伝え、文化を作り、政治に利用されました。戦後は更に普及し、家庭にはその時代の最新技術と流行のデザインで作られたラジオ受信機が置かれました。
写真は1950年代終わりころから、1960年代の初めにかけてヨーロッパで発売されたラジオです。ほんの数年ですが、この間でもデザインは大きく変化しています。
ラジオがまだまだ高級品で「持つこと」に価値があり満足感につながった時代。一番古いPhilips Philettaはそんな頃のラジオの形を伝えています。シンメトリーで装飾的、リビングの一番目立つところで家族に囲まれているのが似合いそうです。しかし、モダンデザインの伝統があったドイツではすぐに直線的なデザインが取り入れられます。 BRAUN TS3では装飾性は極力排除されています。しかし、ダイヤルの配置などはまだ伝統的なスタイルを踏襲しています。 BRAUN RT20 になると、もはやシンメトリーではなくなり、木材や布で作られていたフロント部分も金属で覆われています。白一色で主張しないシンプルなデザインは現在にも通じるものを感じます。
このようなデザインの変化は「ラジオを聴く」という文化が急速に変化したために起こったのではないでしょうか。もちろん、この時代でも「ラジオは聴くもの」だったのでしょうが、それに加えて、いいラジオを所有すること自体が楽しく誇らしいという人も多かったはずです。そういう人たちには、豪華で象徴的なデザインが好まれたのは理解できます。
しかし、やはりラジオは聴くものなので、放送されている内容が重要です。流れてくる音楽やドラマやニュースがやはり肝心なのです。そうすると、生活の中でラジオの「受信機」が主役である必要は無くなってきます。生活の舞台であるインテリアに良く馴染み、操作が分かりやすく簡単であることが重要です。
そんな意識の変化は外観のデザインにも反映されてきます。装飾を排除し、操作もシンプルにという「引き算のデザイン」が行われていきます。この「引き算のデザイン」はメディアとしてのラジオを浮かび上がらせます。「ラジオを聴くってそもそもどういうことなのか?」ということをもう一度考えるようになります。豪華な受信機を置くのが目的ではなく、「ラジオではあのアーティストの音楽が聴ける」「ラジオを聴きながら家族と食事をする時間は最高だ」「ラジオで聴いた株を買って儲けることができた」だからラジオが必要なんだ、という理解が深まっていったのです。
それは「サービス」としての「ラジオ」が本当の意味で定着していくということです。
引き算のデザイン
「引き算のデザイン」はモノやサービスの本当の意味を浮かび上がらせます。ラジオをサービスとしてとらえたとき、それは今までにはない、革命的なサービスでした。国中の人に、時には国も越えて多くの人に、同時に同じ情報を伝えることができるようになったのです。
ほどなくして、テレビが発明され映像も対象になりました。ラジオ局ではテレビ放送も行うようになります。そして、ラジオともテレビとも縁のないところでコンピューターが生まれます。コンピューターは相互に接続を始め、あっと言う間にインターネットが世界を覆いました。インターネットでは情報が双方向に流れます。個人対個人、企業対個人、企業対企業...複雑で大規模であらゆる産業が関連しており、全体を見通すことは、もはや困難です。
そんな現代のメディアの本質も「引き算」することで見えてくるのでしょうか?
もしかするとラジオはそんなメディアを「引き算」した究極の姿なのかもしれません。いくら技術が進んで形態が異なっても、メディアはどこか「ラジオ的」なものを残しているのではないでしょうか。
1906年、夜空に放たれた電波は米国のアマチュア無線家たちに受け取られました。彼らは手製の受信機を念入りに組み立て、雑音の向こうから聞こえるクリスマスソングに耳を澄ませていました。日本のラジオ草創期にもアマチュア無線少年たちが大きな役割を果たします。組み立て式のラジオを作った彼らが日本で最初のラジオ聴取者だったのです。そして、組立ラジオの部品は秋葉原の電気街で調達されました。
秋葉原電気街の発展はラジオの普及とともにありましたが、その後、秋葉原の主役はパソコン少年がとって替わります。もちろん、インターネットの扉をこじ開けたのはこのパソコン少年たちです。
戦前から戦後にかけて手製のラジオを組み立てていたアマチュア無線家と1980年代に現れたパソコン少年たちは何でつながっているのでしょう?それぞれの時代での最新技術を駆使しているという満足感、機械部品やモノづくりへの嗜好というものもあります。しかし本質は、おそらく内向的であった彼らの、距離を超えて見知らぬ他者とコミュニケートしたいという欲望を満足させるのが、ラジオでありインターネットだったのではないでしょうか。
肥大化し社会の様々なものを飲み込んで進化を続けるインターネットも「引き算」すると、見知らぬ他者とコミュニケートしたいというピュアな思いが本質にあるのかもしれません。Facebook、Instagram、Twitter...どれも見知らぬ他者とのコミュニケーションを実現するものです。そんなメディアの原型を最も忠実に残しているのはラジオということになります。だから「ラジオは無くならない」そんなふうに思うのかもしません。
「引き算のデザイン」は製品の外観だけでなく、サービスの本質も思い出させてくれます。
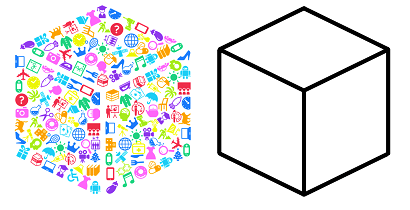




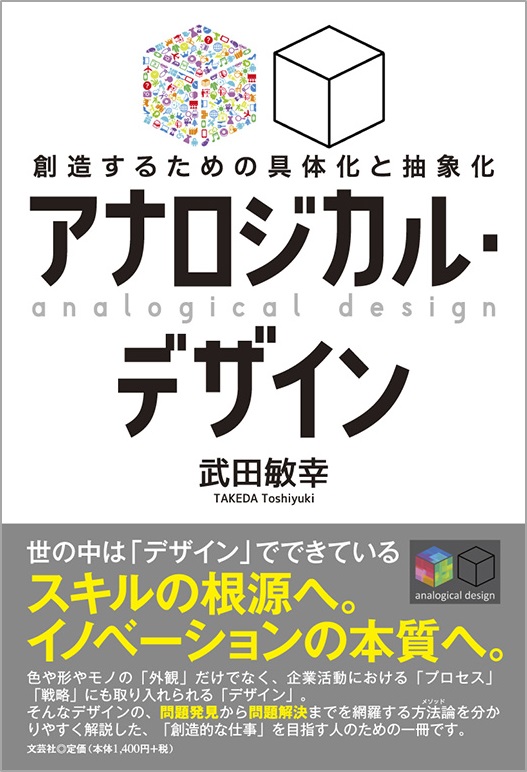



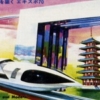



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません